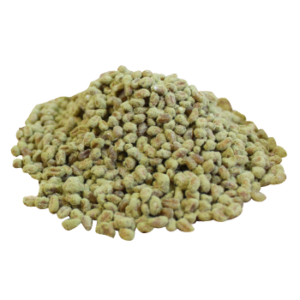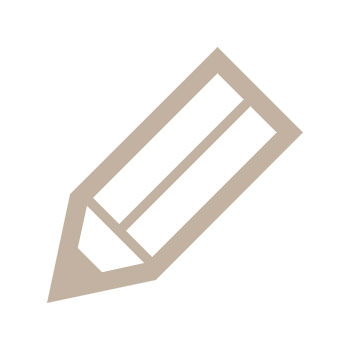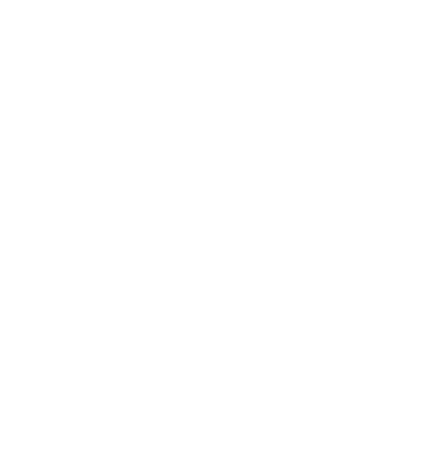菊名あのころ
平成八年、菊名北町町内会で発行した「菊名あのころ」に、叔父 小泉 正が小泉麹屋について語っていますので、引用し、紹介させていただきます。「菊名あのころ」は、郷土の歴史を振り返り語り継ぐために「地域のお年寄りの話をまとめ、忘れかけている昔の暮らしぶりや町の変遷を記録する」目的で制作されました。当時私は28歳、まだ小泉麹屋を継ぐ前でした。叔父が語ったこの2年後に、小泉麹屋 五代目 麹師として家業の再開を決心しました。
菊名あのころ

私は「菊名の麹屋」で通っていますが、分家なんです。本家は菊名五丁目、二四ノ二五の小泉聡さん方で、当主はいま二十八、九歳。その父親の勝徳というのが私の兄ですが、昭和五十八年に四十一の若さで亡くなり、以来、麹屋の仕事は休んでいます。
でも、今でも「甘酒造りたいんだが、麹ありませんか」と時々聞いてこられるんです。麹造りの設備、室や大釜などは今もそのまま残っていますが、このままやめてしまうか、再び始めようかと決めかねているようです。だから造ろうと思えば、いつでも再開できそうな気もしますが、今のこのご時世で、果たして麹造りが営業として成り立つものかどうか、とても疑問です。
昔は、農家はどこでもみそなんか、自分の所で造りましたから、麹が必要でした。甘酒も何かあると、よく飲みましたね。ことに人寄せのとき、お会式とか正月、三月の節句のときなどです。そこでも麹。でも今の暮らしでは、すっかり出番が減りました。
えっ、麹屋の数ですか。うちがやってたときでも横浜じゅうで二軒でした。その本家が休業したので、今は一軒だけ。瀬谷にあります。人口三百万人以上の横浜で一軒だけの商売。貴重な存在です。
私は戦後生まれ。とてもこの本にでる「古老」の資格なんてありませんが、麹屋のことをお話できる人が、ほかにはほとんど居られませんので、叔父の小泉幸次さんに同席していただいて、戦前の事は叔父さんに確認しながら、お話するわけです。
幸次叔父はいま七十四歳。麹造りは、戦前では昭和十五年に軍隊に入るまで、戦後では復員してから昭和二十二年に分家するまでの間、家族として手伝っていました。だから「こうじやのこうじさん」と呼ばれて、いっぺんで人に名前を覚えてもらったようですね。一方、私は生まれてからずーっと麹造り。昭和四十五年に結婚してからも、兄の所が仕事を休むまで、麹造りに汗を流してきました。
本家の麹造りがいつから始まったのか、文献が何も残っていないので分かりませんが、明治か大正になってからでしょう。勝徳の祖父の兄弟が始めたと聞いたことがあります。大正時代にやっていたのは、幸次叔父の伝聞からも確かでしょう。
麹を造る
本家の麹造りというのは、家内工業でした。大きな工場なんてなく、当主夫婦を中心に、家じゅうで力を合わせて造ります。その大黒柱だった兄、勝徳が亡くなったので、本家は続けることができなくなったのです。
麹造りは、いわば農閑期の副業。小泉の家はもともと農家なんで、冬は農閑期です。その十月から翌年の春三月までの半年が、麹造りの季節です。暑い季節は需要がないので造りません。
このことは、千葉県成田山の門前でも分かります。今でもあそこには麹売りが出ていますが、冬の間だけですよ。暑い季節には商品になりません。
家で造っていたのは嘗めもの麹と甘酒麹、みそ麹の三種です。嘗めものとは金山寺みそ、ご存知ですね、ああいうのを造るので、それはメインの原料が麦こうじです。大豆の炒ったものと麦こうじを塩湯に入れると、自然にぶつぶつ発酵、二、三日で食べられるようになる。それが嘗めもので、造るとき甘酒麹を少し混ぜると甘みが出て、とてもおいしくなった。家によっては小さなナスを入れ、キュウリを細かく切って入れたりもした。味も好みによって辛めにしたり、甘くしたり。だから嘗めものにはそれぞれの家の味というのがあって、どこの主婦も「うちのが一番うまくできた」と心の中では思っていた。
不思議なことに、年寄りはどこの家でも秋、涼風が立つころになると嘗めものが食べたくなりました。秋口になると、うちでは嘗めもの麹が売れだす。そうすると「ああ、今年も秋がきたな」。麹屋の店先でも、くらしの歳時記がプーンと感じられたのです。
甘酒麹は甘酒を、みそ麹はみそを造る-そんなことは平成の今でも、どなたもお分かりでしょう。嘗めもの麹を合わせて三種とも麹には違いないが、もとになるタネ、つまり麹菌も違うし、原料も違う。甘酒麹は米が原料ですし、みそ麹は米も麦も使う。出来上がったのを見ても、麦の麹はこがね色だが、米の麹は白い。一目で区別がつきます。
一番大事なのが麹菌。うちでは、京都の麹屋三左衛門というお店から買っていましたが、後には東京・小石川、今の文京区にある日本醸造という会社から買っていました。
造る場所は、わら葺きの母屋の横にある麹棟です。その中に半地下の室がある。半地下なので、麹造りに大事な湿気や温度の具合がいいのです。広さは六畳くらい。昔は土のままだったようですが、昭和四、五年にコンクリートで固めました。
そこでの麹造りですが、まず原料の米や麦を水に冷やす。翌日、十分冷やかされた米や麦をこしきに入れ、大釜に乗せてふかす。それに用意してあった麹菌を混ぜてから、室に入れて、ねかせる。
原料が米なら一晩ねかせ、麦のときは半日ねかせてから麹蓋に盛る。麹蓋というのは浅い木の箱ですが、大蓋と小蓋の二種がある。大蓋はふつう「一升盛り」といって、ふかした原料一升を盛るのですが、大きさは縦六十センチ、横三十センチ、深さ五センチほどのもの。小蓋はその半分の大きさで、五合盛りでした。
この麹蓋の上で混ぜたり広げたり。湿度と温度に注意しながら、3日間で立派な麹の出来上がりです。
湿度と温度の管理ですか。いや、全く経験とカンが頼りで、温度計なんて使わなかった。手で触ってみて、「うん、これならいいな」って調子です。「少し熱すぎるな」となると室の小窓を開けて、外気を入れる。それで結構間に合って、いい「菊名の麹」になりました。
麹を売る
嘗めもの麹、甘酒麹、みそ麹の三種を本家で造って売るのですが、それはいわばオリジナルな製造直売。そのほかに「賃麹」といって、農家の人の委託で造る麹がありました。
農家の人が「これで麹を」といって、米や麦を持ってくる。時にはアワもきました。それを加工して麹にしてあげる。農家の人が取りに来て、うちは加工賃をもらう。それが「賃麹」で、暮れの「賃餅つき」と同じような仕事でした。
戦前の売上は、製造直販と賃麹がほぼ半々。いや賃麹のほうが多かったかもしれませんが、戦後はメインが賃麹になりました。ことに昭和三十年 – 四十年代のころは…。
うちで造った「菊名の麹」は店先で売るほか、戦前は天秤棒で近在の村々を順次売り歩きました。「菊名の麹屋でござい」って調子で、篠原、大豆戸、師岡、太尾から樽、大曽根、綱島あたりまでを一軒一軒回りました。
売るといっても、昔は一部の現金取引を除き、主として物々交換でした。穫れ秋になって、玄米で精算したのです。
麹蓋1枚で玄米いくらいくら-といった交換比率が決まっていて、それで「はい、△△さんとこは何枚」「○○さんとこは何枚」などと、売れた麹蓋の枚数を帳面につけて、玄米をもらう。矢立から筆を取り出して記帳するなんて風景もあったことでしょう。
もらった玄米は南京袋にあけて入れ、次の村へ回って行く。集めた玄米は牛車などで、逐次本家に運びました。今と違って自動車などほとんどない時代だから、邪魔にはならない。売れた枚数を「正」の字に書いて足し算したりしていても、周りから文句は出ない。
売り子は男と女が一人ずついました。売り歩く道筋、日時など、ローテーションが決まっていたのでしょうね。村の祭り、お会式などの時季に合わせて回ったようです。一日売り歩いて戻ってくると、「ああ、今日はよく売れた。三十五枚でした」などと主人に報告、一枚につきいくらと決められた歩合で精算していました。
甘酒のこと
麹の用途で一番需要があったのは甘酒でしょう。戦後も昭和四十年代になって、農家が自家用のみそを造らなくなっても、甘酒だけは造っていたからです。
思い出すのはお会式です。秋十一月三日は妙蓮寺のお会式の日でした。どんつくどんつく、にぎやかなうちわ太鼓の行列が和田根の「はずれ」から出る。和田根は今の菊菜五丁目、旧道沿いの地名。「はずれ」というのは本家の屋号です。
菊名の地付きの家々には今も屋号が残っていて、土地っ子の間では、屋号で話が分かります。「かじやの嫁さんが」とか「たびや」「いんきょ」「なか」などいくらも’生きている屋号’が通用しています。
その日、「はずれ」では大釜に甘酒をわかして、村の老若男女、みんなに振る舞った。日蓮宗に関係がなくても、毎年その日の甘酒進上を楽しみにやってくる人がたくさんいました。
法隆寺も妙蓮寺と同じく日蓮宗で、十月にお会式がありました。ここにもうちから甘酒麹を奉納していました。うちわ太鼓の行列は今の菊名三丁目、屋号を「はら」といった小泉佐太郎さん、当主実さん(この本で聞き書きさせていただいたお一人)の家が出発点でした。
甘酒は菊名神社の初もうでの時にも出しました。うちの奉納でした。甘酒サービスは今も毎年続いていますが、もちろんうちの製品ではありません。
お客で印象の深いのは小机の土井の谷の人たちです。やはり日蓮宗で本法寺というお寺があって、お会式があると村の人がつぎつぎ、うちへ麹を買いにきてくれました。
寒い季節にうれしい甘酒ですが、先日ちょっと調べてみて驚いたのは甘酒売りの季節です。江戸から明治、大正にかけて、甘酒売りという商売があり、天秤棒を肩に町を売り歩いていた-ことくらいは知っていましたが、この商売、夏のものだけだったというのです。
「暑いときこそ熱いもので暑気ばらいを」とのことですが、俳句の季題を見ても、甘酒は確かに夏のもの。でも、菊名の暮らしでは、甘酒は寒い季節と結びついていました。
その造り方も少しお話ししておきましょう。まず甘酒麹一升におかゆ-もちろん米のおかゆを三合くらい混ぜる。それをこたつの中くらいの温かさの中に一昼夜ほどおくと「甘酒のもと」となり、それを薄めて飲むわけです。
薄めるとき若干の砂糖のほか、隠し味の塩を入れると、ことにおいしくなります。薄める前の「甘酒のもと」が好きな人もいて、こっそり指先につけて、なめたりしました。
こたつの中にいつまでも入れておくと酸っぱくなりましたし、原料の混ぜ具合にも気を使います。以外に手がかかるので、インスタントもの全盛の近ごろでは、麹を使って甘酒をなんて人、少なくなるのはやむをえないでしょうね。
麹からみそへ
こうして村人の暮らしを支えてきた麹屋ですが、昭和四十年代から少しずつ需要が落ちてきました。すべて物を自分で造る時代じゃなくなったんです。で、本家では自家製のみそを売り出すようになった。これが本当の「手前みそ」で、商品名もズバリ「自家製の手前みそ」としました。
半年ねかして造った白みそで、混ぜものは一切ありません。これはまことによく売れました。反比例するように麹の売り上げは減り、昭和五十八年、兄の死で営業は休止、みそのほうも惜しまれながらおしまいとなりました。